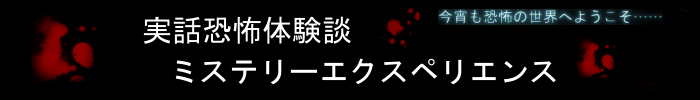TOP > 実話恐怖体験談目次3 > おじぎ
おじぎ
ペンネーム:ホームさん
ホームに向っておじぎをしている男がいる。さっぱりとした髪型の青年で、大学生に見える。身なりに違和感はないのだが、気になるのはその行動だ。
帰宅ラッシュのホーム――自動改札口のすぐ側――に両足をそろえて立っている。そして、上半身を九十度に曲げて、深く深くおじぎをしている。
初めて彼を見たときは、誰か恩のある人の見送りにでも来ているのだろうかと思ったものだ。しかし、毎日ああしているところを見ると、誰かを見送りに来ているわけではないらしい。
ある日の帰宅ラッシュ。私は好奇心に駆られて、その日はあえて彼のすぐ側を通ってみることにした。たくさんの人が行き交う間を縫って、彼に近づく。平静を装い、横目で彼の挙動を伺いながら。
近くまで寄ってみると、遠目で見るよりしっかりした身なりの青年だということが、よくわかる。黒いコートをまとい、髪はきれいに七三に分けられていて、少しも不潔には映らない。その奇妙な行動を除けば、おそらく好感の持てる若者だ。私は歩幅もゆるやかに、彼の前を通り過ぎる。
「――」
野太い声が、耳に響いた。
思わず振り返る。しかし、彼はもう何も語らない。顧みて、初めて直視した彼の肌は、死人の顔に載せる白い布のように色がなかった。
背筋に走る悪寒。震えるほど寒いのに、額には汗がにじみ始めていた。やはり、彼のことを意識したのは、間違いだったのだ。言い知れぬ直感が、理性に告げる。私は足早にその場を立ち去ると、二度と彼に近づかないと決意したのだった。
そんな出来事があった、翌日の帰宅ラッシュ。氷の粒のような真冬の小雨が、プラットフォームを湿らせている日であった。
私はいつものようにサラリーマンに混じり、ホームに電車がやってくるのを待っていた。たまたま、電車が行ってしまったばかりだったので、しばらく待ちぼうけを食らうのは、間違いない。
かばんから読みかけの文庫本を取り出し、目を通していると、隣に人影が重なった。何の気なしに、様子を伺う。思考は一瞬にして凍りついた。思考だけではない。ページをめくる指先も、その衝撃の重さに堪えきれず感覚を失う。
すべては私に寄りそうようにして、ホームにおじぎをして立っている男のせいだった。そう、今日に限って彼は、いつもの自動改札口の側から離れ、私の隣に佇んだのである。昨日、私が彼の様子を探ったように、今度は彼が私に興味を持ったのである。
恐怖は最高潮に達し、早くこの場を離れたいのだが、脚が言うことをきかない。足に枷でもつけらたかのようだ。
――と、プラットフォームに響くアナウンス。間もなく私の乗る電車が、やってくる。よかった。これに乗り込んで、早くここを去ろう。トンネルの向こうに光が見えた気がした。
おじぎしている青年はと言うと、相変らず直立不動で、身じろぎひとつしない。が、ひとつだけ変化があった。口元に笑みを浮かべている。何がうれしいのだろう。
線路の向こうから警笛がひとつ。ああ、電車がやってくる。もうすぐ、この場から立ち去れる。電車は、ゆるやかに近づいて来る。その時、青年が走った!
おじぎをしたままの体勢で、プラットフォームの黄色いラインを越える。
「危ない!」
思わず叫んだ。すでに青年は、身を線路に投げている。電車のブレーキなど間に合うはずがない。彼の四肢は勢い良く、跳ねられ、車両の下に消えた。
電車はいつもの停車位置の落ち着くと、穏やかにドアを開ける。人々に恐怖の色はない。皆、普段どおり電車に乗り込み、駅員の表情も変わらなかった。私の叫びは雑踏に漂い、そして静かに霧散した。
発車ベルが鳴り、身をゆすりながら電車は走り去った。最後まで何事も起こらなかったのだ。私はおずおずと、線路ににじり寄り、彼がどこへ消えたのか確かめようとして――やめた。タクシーで家路に着いて以来、いまだに私はその駅に近づきすらしていない。
【実話恐怖体験談募集】あなたの実話恐怖体験談をお待ちしています。
実話恐怖体験談募集要項
実話恐怖体験談を投稿する